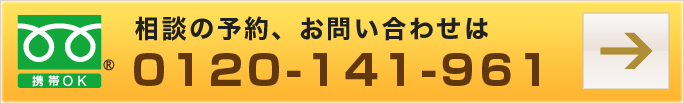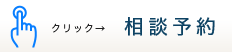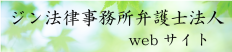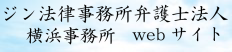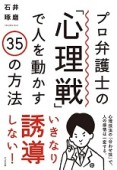離婚と婚姻費用
裁判例
年収1億円の婚姻費用(東京高裁平成29年12月15日決定)
年収1億円の婚姻費用についての裁判例紹介です。
婚姻費用は婚姻関係がある夫婦間で、収入が多い方から少ない配偶者に対して支払う生活費等のこと。
コンピと言われたりします。
その金額について争われた東京高裁平成29年12月15日決定の紹介です。

事例
年収1億円以上あるようなケースで婚姻費用が争われた事例です。
夫の年収1億5000万円
妻はゼロ。
婚姻費用の請求を妻から夫に対してしたものです。
原審では月額120万~125万円と認定。
夫がこれを不服として東京高裁へ。
高裁では月額75万円に減額されました。
ただし、このほかに夫の関連会社等が所有している住居に妻が住んでいるということです。
その住居費が月330万円というような話もあります。

婚姻費用計算の根拠?
通常、婚姻費用を決めるときには、算定表が使われます。
お互いの収入や子の年齢で算出します。
その算定表の元になっているのは標準算定方式という計算方法です。
ただ、この算定表は、基本的に年収は2000万円までを想定していています。
これを上回るような収入の場合には使いにくいです。
では、どのようにして算出するのかというと、各裁判官の判断が分かれます。
標準算定方式に近いような算出方法で計算する人もいれば、個々の生活状況によって金額を判断する人もいます。
今回の高裁の判断では、生活状況などから金額を算出するという方法で認定しています。
住居の負担等の生活状況を考えて、月75万円と認定しています。
その裁判所の決定文の中では、婚姻費用の趣旨は、生活費負担にあり、贅沢な生活を保障するものではない、とも書かれています。
「一般に,婚姻費用分担金の額は,いわゆる標準算定方式を基本として定めるのが相当であるが,本件では,義務者である抗告人が年収1億5000万円を超える高額所得者であるため,年収2000万円を上限とする標準算定方式を利用できない。高額所得者については,標準算定方式が予定する基礎収入割合(給与所得者で34ないし42パーセント)に拘束されることなく,当事者双方の従前の生活実態もふまえ,公租公課は実額を用いたり,家計調査年報等の統計資料を用いて貯蓄率を考慮したり,特別経費等についても事案に応じてその控除を柔軟に認めるなどして基礎収入を求める標準算定方式を応用する手法も考えられる。しかし,抗告人の年収は標準算定方式の上限をはるかに上回っており,職業費,特別経費及び貯蓄率に関する標準的な割合を的確に算定できる統計資料が見当たらず,一件記録によっても,これらの実額も不明である。したがって,標準算定方式を応用する手法によって,婚姻費用分担金の額を適切に算定することは困難といわざるを得ない。
そこで,本件においては,抗告人と相手方との同居時の生活水準,生活費支出状況等及び別居開始から平成27年1月(抗告人が相手方のクレジットカード利用代金の支払に限度を設けていなかったため,相手方の生活費の支出が抑制されなかったと考えられる期間)までの相手方の生活水準,生活費支出状況等を中心とする本件に現れた諸般の事情を踏まえ,家計が二つになることにより抗告人及び相手方双方の生活費の支出に重複的な支出が生ずること,婚姻費用分担金は飽くまでも生活費であって,従前の贅沢な生活をそのまま保障しようとするものではないこと等を考慮して,婚姻費用分担の額を算定することとする。」
同居中に贅沢ができたからといって、婚姻費用でそれが保障されるわけではないという判断です。
年収1億円の人で、婚姻費用で争われそうという方は、ぜひご相談ください。