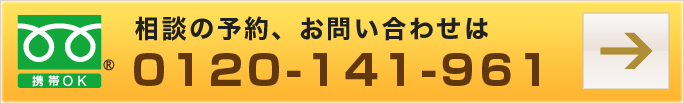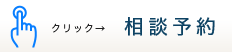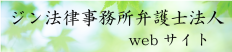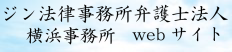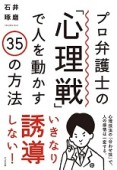FAQ(よくある質問)
よくある質問
Q.離婚裁判の訴状のポイントは?
離婚裁判に関し、東京家裁人訴部における離婚訴訟の審理モデルが公開されていました。その中から、離婚裁判の訴状の記載などを取り上げて解説します。
東京家裁とはいえ、神奈川県でもポイントは同じですので、チェックしておきましょう。
この記事をチェックすると良い人は、次のような人。
- ・離婚裁判の準備中
- ・離婚裁判の訴状を作っている人
離婚訴状での離婚原因
離婚裁判の訴状作成時には、離婚請求原因として民法770条1項5号(婚姻を継続し難い重大な事由)を記載することが重要です。
法律が決めている離婚事由には、具体的に不貞行為(1号)や悪意の遺棄(2号)などがあります。
しかし、これらの事情だけでなく、5号を明記して含めておくことが重要とされます。
これにより、離婚請求原因の審理を省力化できるのが理由とされます。
たとえば、長期間の別居などから婚姻関係の破綻が明らかな場合、5号の記載があれば早期に財産分与の審理に入ることができるとされます。
離婚訴状には別居の記載
訴状には別居に関する情報も明記するのが良いとされます。
具体的には
・別居開始日
・別居に至る直前の経緯
・別居の直接の原因
・どちらが自宅を離れたか
・子どもを連れて出たかどうか
などです。
これらの情報は、裁判所が事案の全体像を把握するために有効とされますので、訴状段階で記載しておくようにしましょう。
離婚訴状は客観的な事実を
離婚原因として、婚姻を継続し難い重大な事由などの記載をしようとすると、あまりにも主観的な主張を書きたがる人も多いです。
感情的になるのはわかりますが、家庭裁判所からは、客観的事実、簡潔な事実関係の記載をするよう求められます。
主観的評価や、過度に詳細な事実の列挙は控えたほうが良いでしょう。
感情的な訴状を提出すると、紛争が長引く可能性も高まります。
離婚裁判で請求できるもの
法的に、人事訴訟で請求できないものは、離婚訴状の請求の趣旨には含められません。
離婚請求、親権者指定、離婚慰謝料、財産分与、養育費などは問題ありません。
裁判所からNGを出されるものとしては、特有財産に係る物の引渡し請求、不当利得返還請求などです。
このような請求は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所や簡易裁判所の管轄事項とされます。
人事訴訟の関連請求として請求すると、移送の問題が生じ、期日指定が遅れる可能性があります。
離婚調停の経過と予想される争点
離婚裁判は、調停前置と呼ばれ、離婚調停後に行うのが原則です。
そこで、離婚裁判の訴状には、調停の経緯も記載するよう求められます。
調停の時期、調停での争点、決裂した原因、裁判でも予想される争点などです。
離婚裁判と秘匿申立ての準備
原告の住所等を被告から秘匿したい場合は、注意が必要です。
提出書類中の秘匿希望住所の適切なマスキングを忘れないようにしましょう。
秘匿の要件となる「社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれ」に関する十分な疎明資料の準備が必要です。
第1回口頭弁論期日
離婚裁判も、通常の裁判と同じく、離婚訴状を出すと、第1回口頭弁論期日が指定されます。
その際、相手にも弁護士がつけば、今後の審理計画や、予想される争点、各争点についての主張・立証の予定を伝えることも多いです。
裁判の進め方を確認することで、全体的なスケジュールを確認できるでしょう。
多くの事件では、主張反論を2往復程度させることで、当事者の主張すべき事実や客観的な証拠関係はほぼ出尽すとされます。
その後も主張反論を希望する場合には、双方に陳述書を提出させることで終わらせられることもあります。
家庭裁判所調査官による調査
親権者の指定に関する審理では、家庭裁判所調査官による調査が必要になることがあります。
この調査は、財産分与等の争点整理が終了する頃にされることが多いです。
これは、判決には、できるだけ最新の調査結果を反映させるためと言われます。
予備的財産分与申立ての時期
予備的財産分与の申立てについては、離婚請求をされた被告からの申立です。
離婚請求自体を争うものの、離婚請求が認められるときに備えて、財産分与の申立をしておくというものです。
不貞をした側から離婚請求をされた場合に、有責配偶者だから認められないと反論しつつ、財産分与の申立を一応しておくという方法です。
このような予備的財産分与が裁判終盤になって出されると、審理予定が崩れるため、裁判所からは、遅くとも離婚請求原因及び有責配偶者の抗弁の争点整理が終了する頃までに、申立てをするかどうか決めるよう言われます。
このような予備的財産分与の審理が必要かどうかは、離婚請求が認容される見込みがあるかどうか、和解による終局的解決の可能性があるかによって変わるでしょう。
離婚訴訟は、どのくらいの期間で終わりますか?
離婚訴訟の期間は、争点や当事者の協力状況によって大きく異なり、数ヶ月から数年かかる場合もあります。
特に、財産分与や親権争いがある場合は、長期化する傾向があります。審理を迅速に進めるためには、当事者間で争点を絞り込み、証拠を早期に提出することが重要です。
財産分与とは何ですか?
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚時にそれぞれの貢献度に応じて分けることです。 財産分与の対象となるのは、預貯金、不動産、車、保険、退職金など、夫婦共有財産と認められるものです。
財産分与の対象財産には、どのようなもの?
財産分与の対象となるのは、原則として婚姻中に夫婦で協力して取得した財産です。
預貯金
不動産
自動車
株式
生命保険の解約返戻金
退職金
ただし、婚姻前から所有していた財産や、相続や贈与によって取得した財産は、特有財産として原則対象外となります。
特有財産とは何ですか?
特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻中であっても、相続や贈与によって取得した財産のことです。 特有財産は、財産分与の対象とはなりません。
婚姻前の財産: 婚姻前に取得した財産は、原則として特有財産とみなされます。
相続や贈与: 婚姻中であっても、相続や贈与によって取得した財産は、特有財産とみなされます。ただし、贈与者が夫婦のどちらに贈与したのかが争点となる場合があります。
特有財産であることを主張する場合は、証拠によって立証する必要があります。
親権者を決めずに離婚できますか?
いいえ、できません。未成年の子供がいる場合、親権者を決めないと離婚は認められません (人事訴訟法32条3項)。
親権者をどちらにするかについては、子の福祉を最優先に考慮して決定されます。
離婚裁判に関するご相談(面談)は、以下のボタンよりお申し込みください。