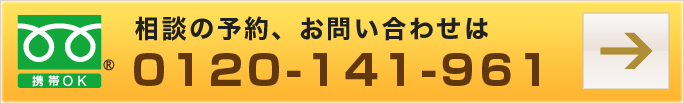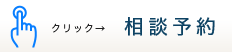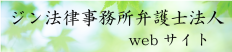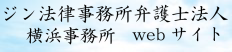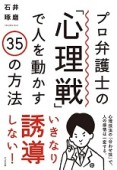FAQ(よくある質問)
よくある質問
Q.離婚訴訟の調停前置主義とは?
離婚手続きの中では、調停前置主義という言葉が出てきます。
交渉での離婚ができなかった場合、裁判を起こせるかというと、そういうわけではなく、まず調停をしなければならないというルールです。
調停前置とは?
現状、日本における離婚は「調停前置主義」が採用されています。
離婚を希望する場合、裁判を最初からできるのではなく、まず、調停をしなさいという制度です。
DV事件などでも、原則、調停から始めることになります。
離婚調停に相手が出てこなかった場合、あらためて裁判の手続きとなります。
このような調停前置主義が採用されているのは、家庭内に関する訴訟事項を、いきなり裁判手続によって、公開の法廷で争わせることは、望ましくないからです。
多くの場合、家庭内の問題は、調停員の助けを得たうえでも、当事者の協議で解決するのが相応しい紛争と位置づけられているのです。
調停をしないで裁判を起こすと?
調停をしないで裁判を起こしたとしても、一応受付はされます。
調停を経由していないという理由だけで受け付けが拒絶されるものではないです。
ただし、その後、訴訟を担当する裁判所が、適当でない場合を除いて事件を調停に付することとされています。
裁判を起こしたのに、結局は調停手続になる、しかも、その審査等に余計に時間がかかるため、最初から調停をした方が早かったということもあります。
調停前置の例外は?
どんな場合にも調停をしなければならないかというと、必ずしもそうではありません。
最も問題ないのが、相手が行方不明で調停が意味をなさないとき。
調停は話し合いですので、そもそも、調停の連絡ができない行方不明者であれば、調停を申し立てる意味がありません。
訴訟から始めることができます。
また、あまりにも暴力的など調停を実施することが不可能なときにも、訴訟提起ができるとされます。
調停が取り下げで終了している場合には?
離婚調停が、調停不成立となっていれば、訴訟提起ができます。
では、不成立ではなく、取り下げになっている場合はどうでしょうか。
超低不成立であれば、家庭裁判所で話し合いをしたもののまとまらなかったことがわかります。
これに対して、取り下げは、申立人側の行為のため、必ずしも不成立と同視できるわけではありません。
しかし、取り下げでも、実質的に調停活動がされたような場合には取り下げでも、調停を経たこととされる扱いになっています。
調停員によっては、話し合いがまとまらないときに、取り下げを促すこともあり、取り下げだから調停をしていない、もう一度調停をしろというのは、あまりにも不合理でしょう。
数回の期日が開かれ、双方が出席したような場合には、取り下げでも問題視されるリスクは少ないでしょう。
調停から時間が経っている場合には?
前回の調停から時間が経っている場合には、調停不成立として訴訟を起こせるかは問題になります。
婚姻関係の状況が変化しており、調停をすればまとまる可能性があるとも考えられるからです。
数年というような長期間が経過しているような場合には、調停時から状況が変わっていないことを訴訟提起時に説明しておく必要はあるでしょう。
そのような場合でも、家庭裁判所が職権で調停に付すという扱いをする場合もあります。
調停の結果は、裁判に引き継がれる?
このように、調停前置主義によって、調停からの裁判という流れを見ると、離婚当事者からすると、裁判では、調停の結果が当然に反映される、考慮してもらえると考えるかもしれません。
しかし、そのような制度設計にはなっていません。
調停不成立の場合でも、訴訟へ当然に移行するものではありません。
新たに訴状を作成、提出して、訴えを提起しなければ、裁判は始まりません。
そして、調停と裁判は別手続です。
調停段階で提出された資料が、当然に訴訟手続に引き継がれるわけではありません。
証拠として考慮してもらいたい場合には、当事者において、改めて書証として提出し、口頭弁論に上程するのが原則です。または事実の調査の資料として提出という方法もあります。
調停時に、親権者紛争などで家裁調査官による調査がある場合、その報告書の内容を訴訟で考慮してもらいたいという場合には、訴訟手続で証拠提出が必要です。
調査官報告書の謄写手続
調査官報告書は、自動的に送られてくるものではありません。
これを証拠で使いたい場合、調停を担当した家庭裁判所に対し、家庭裁判所調査官作成の調査報告書の閲覧謄写を申請し、許可をもらって謄写し、証拠提出する必要があります。
一般に、家庭裁判所の記録については、事件関係人の申立てにより、相当と認めるときは、閲覧謄写を許可することができるとされています。
家事事件記録の秘密性があるため、誰でも閲覧できるものではないのです。
この秘密性と開示を必要とする理由とを比較衡量して、許可するかどうか判断しています。
調停段階において、親権者紛争であった場合には、後の訴訟手続で利用される可能性も前提に、家庭裁判所調査官が、監護状況や子どもの意向等を調査し、報告書を作成していることが多いです。
このような場合には、離婚訴訟の当事者からの閲覧謄写申請が許可される可能性が高いです。
離婚調停での意見変更
離婚調停で意見変更が途中でできるか質問されることもあります。
たとえば、一度不成立の希望を出したが、撤回できますか、という質問です。
離婚調停は、家庭裁判所を通じた話し合いの場です。
話し合いが不可能だと判断された場合には、不成立、不調となります。
たとえば、一方がどうしても離婚したいと希望していて、他方はどうしても離婚したくないという希望の場合、この希望が変更しないと判断されれば不成立になります。
ただ、調停員は、この希望が変更されるかもしれないとも考えます。
そこで、直ちには、不成立にならない事件も多いです。
調停について、次回期日が指定されているのであれば、意見が変わるかもしれないということを前提に、話し合いが続けられることになっています。
一度出した不成立の希望も撤回できます。
次回期日の指定がある場合には、裁判所は話し合いの継続を探っている状況です。
不成立希望の撤回をあえて拒む可能性は低いです。
これに対し、既に不成立で調停が終了している場合には、撤回して再開することはできません。
再度の話し合いを希望するのであれば、改めて調停を申立てするか、調停外で協議をするほかありません。
離婚訴訟、人事訴訟に関する強制執行等のご相談は、以下のボタンよりお申し込みください。