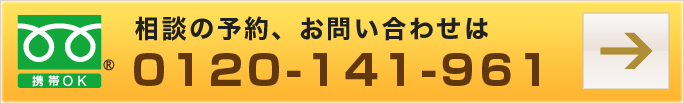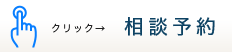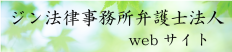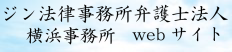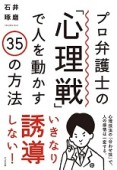FAQ(よくある質問)
よくある質問
Q.離婚すると子供の寿命が短くなる?
子供がいる夫婦の離婚では、子に関する争いも多いです。
親権、監護権、養育費、子名義の財産など。
そのような離婚紛争は、子の環境を変えるだけではなく、子供にいろいろな影響を与えているという研究結果があります。
見逃せないのが、子の寿命に影響があるというデータです。
離婚が子供に与える影響は?
離婚は、親権問題、環境の変化等によって、子どもへ大きな影響を及ぼすことは多いです。
それ以外に、子どもの寿命にも影響があるのではないかという実験データがありますので、紹介します。
『真面目な人は長生きする』(岡田 尊司 著)
という本の中で詳しい話が紹介されています。
幻冬舎
売り上げランキング: 315,302
離婚が、短期的視点で、子どもの精神状態や行動に影響するという話はあります。
それ以上に、長期的視点で影響があるかどうかはわかりませんでした。
長期間、数十年を追いかけることは難しかったわけです。
しかし、本の中で紹介されている、ターマンーフリードマン研究では、この影響を調べてくれています。
親の死と子供の寿命は?
親の死が、子の寿命に与える影響を調べたところ、直接的な影響はないという結論でした。
子ども時代に親が亡くなってしまった場合には、子どもに大きな動揺を与えることではありますが、長期的な視点からは、その影響を子どもは克服するのだそうです。
死亡率の上昇、平均寿命の短縮といった結果にはならなかったそうです。
親の離婚と子供の寿命は?
これに対し、両親の離婚は、親の死亡以上に、子どもの健康に影響を与えるそうです。
実験結果を平均すると、両親が離婚した子どもの寿命は、離婚せずに両親が揃っていた家庭の子どもより、5年程度短くなっていたそうです。
他の因子を調べても、子どもの寿命にもっとも影響を及ぼすのが、親の離婚であったとの結果です。
他の因子として、子供の性格が影響を及ぼしている可能性も検討されました。
たとえば、子の性格に問題があるから両親が離婚になってしまったという関係です。
調査の結果、子の性格と、両親の離婚については、それぞれ独自に子どもの寿命に影響を及ぼしているという結果でした。
子の性格に問題があろうとなかろうと、親の離婚により、寿命に影響するとの結果だったのです。
影響を与える親子関係は?
イメージすればわかることですが、離婚によって親子関係が影響を受けます。
ときには親子関係が断絶してしまうこともあります。
これによる子への影響としては、もともとの親子関係が良好であるかどうか、強固なつながりだったかどうかも関係してくるでしょう。
両親と子との結びつきが強い関係であればあるほど、離婚によって受けるダメージは大きいそうです。
男女差でいうと、男の子の方が影響が強いという結果でした。
子にそんなにダメージを与えてしまうなら、離婚は我慢しようかと考える人もいるかもしれません。
しかし、研究結果からは、離婚前から、親子の愛情や結びつきが稀薄なケース、両親のいがみ合い等で家庭環境が不安定だったケースでは、それほど影響はなかったそうです。
感覚的に、DV、虐待のような家庭環境では、そこから抜け出した方が子のメンタル面にも良い気がしますが、研究結果もこれに合った結果となっています。
研究の時代性は?
本の中で紹介されている研究は、その時代性から、まだ離婚が多くなかったという背景もあります。
そのため、離婚した両親の子は、母子家庭、父子家庭として、肩身の狭い思いを強いられ、それにより子がストレスを受けたという可能性もあります。
そうだとすれば、最近では、母子家庭、父子家庭が珍しくなくなり、影響は少ない可能性もあります。
ただ、残念ながら、最近の研究でも、離婚が、子の精神面に有害な影響を与える傾向は認められてしまっており、長期的な影響も確認されているそうです。
そうだとすると、親子関係がさほど悪くない家庭での離婚については、子の寿命への影響という点も考えて意思決定した方が良いのかもしれません。
父親の不在が影響している?
本の中では、父親の不在という点が、子に影響を与えているのではないかという指摘がされています。
紹介されている研究では、出生時に、両親が離婚していたり、死別しているという場合でも、40代の死亡率が1.7倍になったそうです。
幼少の頃の父親の不在が、将来の死亡率に影響するとは驚きです。
離婚の際の親権、監護権は母親に行くことが多く、離婚家庭の多くは、父親不在となっていることからすると、このデータは意識しておいた方が良いでしょう。
子の寿命に影響する原因は?
なぜ離婚が、子の寿命に影響するのでしょうか。
研究結果では、その分析までされています。
考えられそうな要素としては、離婚により家庭の経済面が悪化し、貧困家庭になってしまったから、という話がありそうです。しかし、これらの要素は、それほど影響していなかったそうです。
要因としては、学歴であるとか、子自身の暴力性なども挙げられています。
しかし、研究結果で、寿命に影響する原因として大きな要素となったのは、喫煙や飲酒でした。
親の離婚で、子どもの喫煙や飲酒が増えた結果、寿命が縮まっているのではないかという話です。
喫煙や飲酒は寿命を縮める要因とされていました。
研究結果では、親が離婚した人は、喫煙や飲酒の頻度や程度が増加していました。女性でこの傾向がより多くみられました。
親が離婚した女性は、ヘビースモーカーになるリスクが2倍以上だそうです。
タバコが健康に良くないことは明らかです。
離婚する際には、子に喫煙や飲酒習慣を持たせないよう努力することで、マイナス面を回避できる可能性も高いです。
そうであれば、まず、親がこれらの習慣を持たない、見せないよう意識した方が良いかもしれません。
子ども自身の離婚可能性が上がる点は?
実は、親が離婚していた人は、そうでない家庭の出身者よりも、その人自身が離婚する可能性が大幅に高いとされています。
つまり、離婚家庭で育っている人は、自分も離婚しやすいとなるわけです。
経験があることの方が、行動に移す際に抵抗は少ないです。
親が経験しているのであれば、離婚家庭がどのようなものであるのかイメージできますし、片親でも問題ないと考えることも多いでしょう。
しかし、自分が離婚しているという点も、自分の寿命に影響するという結果が出ています。
とくに男性の場合に影響が大きいという結果です。
離婚しても子の寿命を維持するには?
子の寿命のことを言われても、信憑性があるか疑問だし、そもそも自分のためには離婚したい。
そんな気持ちの人も多いでしょう。
そのような場合には、この研究結果が信憑性があることを前提にしても、子への悪影響をなるべく減らす方向で動くのが良いでしょう。
上記のように、子の寿命を減らす要因がある程度は限定されているのですから、それを避ければ良いことになります。
まずは、子ども自身が安定した結婚をすること。そして、喫煙などの悪習慣の排除。
過去の家庭の破綻というマイナスのダメージがあっても、その人自身が安定した家庭を築けば、そのマイナスダメージを克服できるとされます。
安定した家庭を築けるようになるためには、愛着がポイントになると本の中では書かれています。
愛着については、この著者の別の本でも詳しく書かれているので、チェックしてみると良いでしょう。
光文社 (2016-11-17)
売り上げランキング: 8,064
離婚のご相談は、以下のボタンよりお申し込みください。